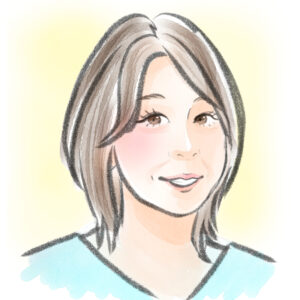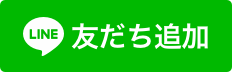こんにちは。
こころ穏やかメンタルサポーターの 池原ゆうです。
先日、こんなご相談を受けました。

「自分の意見が正しいのか、間違っているのかが気になるし、
いい方法をネットや本で探して見つけていろいろ試してみるんですけど、
他の人が、どんな子育てをしているのかもとっても気になるんです。
それに、うちの子を他の子とどうしても比べてしまうんですよね・・・。」
その方は、
お子さんのやることなすことに、
「宿題やった? え、まだ、やってないの? 宿題をやってからゲームだよ」
お子さんと買い物に行って、
「あら、それにするの。こっちの方がいいんじゃない?」と言いたくなってしまうのだそうです。
私も、仕事柄これまで高校生から進路の相談を何度も受けていますが、子どもさんの進路のことでも、親御さんの方が自分の思いや考えを通そうと、気持ちを曲げない方も少なからずいらっしゃいます。
「美容関係の専門学校に行きたいんだけど…。」というと
「え、美容?なかなか大変な仕事だよ。 絶対に4年生の大学にいくべきだよ。」
そんな風に何度も何度も言われいると「大変だし、やっぱり無理なのかな・・・。」と不安になって来て、だんだん何がやりたいことなのかわからなくなってくる。
「うちの子、このままで大丈夫かしら? こういう道に進んだ方がきっと選択肢が広がるし・・・。」
「このままだと、子どもの将来が不安だから…、進路のこともいろいろ資料を探してあげないと。」
これは、過保護でしょうか。それとも過干渉なのでしょうか。
よく過保護と混同されがちなのですが、過干渉とは一体どのようなものなのでしょうか?
過干渉とは
親の願望を子どもに押しつけたり、子どもの人生をコントロールしたりするのを「過干渉」といいます。子どもの人生でありながら、自らの『こうあるべきだ』が強く、それが干渉という形で出てしまいます。
また、中には、親御さん自身の自己肯定感の低さから『子どもができることがが自分の評価につながる』かのような思いを抱えていて、『自分の思っている理想の子』に育てようと干渉し過ぎてしまう場合もあるようです。
一方、過保護というのは「わが子が嫌な思いをすることに耐えられず、本来であれば年齢的に我慢して乗り越えさせるべきことでも、自分自身がそれを先回りしてお膳立てしたり、肩代わりして責任を取ったりしてしまうこと」です。
『そんな状況になったら、あの子がかわいそうだ』という思いが強くあって行動してしまった結果、過保護になってしまっているともいえるでしょう。
親であるあなた自身が、自己肯定感が低く「私のような思いはしてほしくない」という思いから、先へ先へと子供の将来を考えて一生懸命になるあまり、先走って行動してしまっていることもあるかもしれませんね。
子どもの頃に両親からいろいろ言われて嫌だった経験がある、自分は反面教師にしたいという思いはあるけれど…
子どもを目の前にすると、つい、あれこれ口を出してしまう・・・という場合もあります。
そこには「自分が思い描く理想の子どもに育てたい」というコントロール願望が潜んでいるかもしれません。
【過干渉 チェックをしてみましょう!】
✅子どもの時間割を毎日確認、率先して準備をする
✅子どもが着る服や持ち物を勝手に選ぶ
✅子どもが嫌がる習い事を無理に続けさせている
✅子どもの宿題に口を出しすぎてしまう
✅子どもの進路を勝手に決める
✅子どもの交友関係が気になって口を出してしまう
✅子どもの行動を逐一チェックする
✅子どもの机の引き出しをこっそり開けてしまう
✅子どものメールを盗み見してしまう
✅子どもをほめるよりも叱ることの方が多い
✅子どもの行動によく「〇〇した方がいいよ」と言ってしまう
などです。
あなたはいくつ当てはまりましたか?
ちょっとここで、立ち止まってみてくださいね。
そのままの子育てを続けていると、お子さんはどのように育っていくと思われますか?
過干渉の子育てがもたらす影響
過干渉なしてしまうと…
過干渉で子育てをしてしまうと次のような影響が出てしまうことがあるのです。
1.自己アイデンティティが育たない
親が子どもの生活のほとんどを管理し、子どもが独自の経験や意志を発展させる機会を奪ってしまうと、子どもの自己アイデンティティ(自分らしさ・自分が自分でいいんだという感覚)がうまく育たず、自己認識や自己価値感が低下していきます。
そのため、自分が望んでいると思っていることが本当に自分の望むことなのか、それとも親が望むことなのかよくわからない…という状態になってしまいます。
2.自己効力感の低下
親が子どもの代わりに問題を解決し、困難な状況になるのを防ごうと先回りして行動させることが多いと、子どもの自己効力感が低下することがあります。
失敗に対する耐性が弱く、一度の失敗で心に大きな傷を負ってしまい、失敗をおそれるようになってしまうことがあります。他者からの評価に過敏になるなど、自分で問題を解決できる自信がなく、依存的な性格になってしまう可能性もあります。ときどき無力感におそわれてしまうなどの弊害も。
3.対人関係の問題
親が子どもの友達や恋愛関係などに干渉しすぎると、子どもは他人との関係を築く能力が育たなくなってしまいます。
また、親が他の人々との対話や交流にあれこれ口をだしてしまうと、子どもの社交性のスキルが育ちません。
友だちや周囲の人間との距離感をうまくつかむことができず、人間関係でのトラブルを起こしがちになることもあります。親の過干渉な言動は、子どもに「親は自分を信頼していない」と感じさせてしまうために、子ども自身も他者を信頼できなくなってしまうのです。
4.ストレスと不安の増加
親が常に子どものことを心配し過度に監視することは、子どもに子どもは自分の行動や選択に対してプレッシャーを感じたり、ストレスや不安を引き起こすことがあります。
自分の考えを押し付けてくる親に対して、「私はこうしたい」という交渉ができずにたまってしまっていた怒りや悲しみの感情から、親に対する反抗的な態度や精神的な問題につながってしまうこともあるのです。
5. 自立性の欠如
親が子どもの生活を過度に管理すると、子どもは自分で何かをする機会を失って、自立することができないまま成長してしまいます。これが将来の自立の妨げとなり、自分自身で生活することが難しくなっていしまいます。
子どもを保護したりサポートしたりすることは大切なのですが、
過干渉な子育てをしてしまうと子どもの健全な発達に悪影響を及ぼす可能性があるのです。
お子さんが成長していく過程で、自分自身で考えて決めさせるという機会を与えることはとても重要です。
子どもの成長を願うなら、一番大事にするのは「子どもの気持ち」であり、親の理想を押しつけることは親の自己満足でしかないのです。
お子さんの自立の芽を育てるためにも、干渉はほどほどにしたいですね。
子育てで大切なこと
子どもの成長に合わせて、子どもが考えて決めるべきところは子どもに決めさせることが大切です。
子どもが行動してみて、立ち止まったとき、困ったとなどは、
相談役やサポート役になることが大切。
(ほうっておくのではなく、子どもの行動や決断を近くで見守っていて、
悩んでしまったり、くじけそうになったりした時には手を差し伸べる感じでしょうか)
お子さんの持つ力を信じて、境界線をしっかりと引きながら、お子さんが自身で考えるべきことなのか、それとも親が行動すべきところなのかをよく考えて、バランスを取ることが大切になってきます。
お子さん自身が自分で学び、成長する機会を大切にしていきたいものですね。

あなたは、ご自分が子どものときに、母親や父親、または両親の過干渉で悩んでこられませんでしたか?
または、その反対で両親が忙しい、自分のことで精いっぱいなどの理由で、まったくかまってもらうことがなかったために、「自分自身があの時にしてほしかったことを我が子にしてあげたい」という一心で、あれこれと理想の子育てをしようと頑張ってしまっているのかもしれませんね。
干渉しすぎてしまうと、お子さんが、あなたの言動で傷ついたり反抗する気持ちが抑えられなくなったり、不安を増長してしまう場合もあるのです。
まずは、その「癖」に気づくことが大切です。気づいて、悪循環から抜け出していくことが大切です。
初回相談ではあなたのお悩みを丁寧にお聞きすることで、
あなたが幼いころやこれまでの人生の中で身につけてきた「心の癖」にも気づいて整えていくことで、ご自身の自己肯定感を育みながら子育てをしていくということができます。
自己肯定感は何歳からでも育てていくことができます。
不思議なことに、それと同時にお子さんへの過干渉が自然と減っていくことに驚かれる人もいます。
ご自身の自己肯定感を高めながら、
お子さんの自己肯定感を育む子育てを楽しんでいきませんか。
子育て こころ穏やか カウンセラー 池原の詳しいプロフィールはこちら

”こころ 穏やかカウンセリング” では『お試しカウンセリング』を受け付けています。
限られたお時間ではありますが、あなたのお話をじっくりお聴きし、あなたに合った解決策についてご提案をさせていただきます。
お試しカウンセリングは、限定5名様まで
通常90分 15,000円 → 特別価格60分 2 ,000円
(価格は予告なく変更することがあります)

ご予約お待ちしております
こちらから予約できます↓